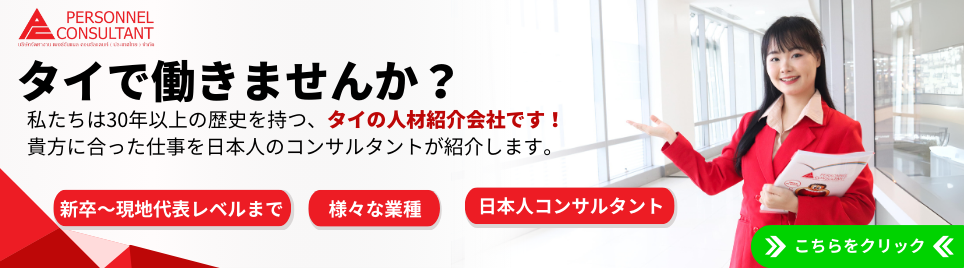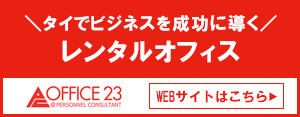「マイペンライ」寛容なタイ社会の真実
「マイペンライ」という言葉は、「大丈夫」「お構いなく」「気にしないで」といった意味を持ち、寛容なタイ社会を象徴する表現としてよく知られています。この言葉は、マイペンアライ(なんでもない・大丈夫)が変化したもので、疑問形ではペンアライマイ?(大丈夫ですか?)となります。しかし、この言葉には表面的な意味だけでなく、タイ社会特有の価値観や考え方が反映されています。
「マイペンライ」に込められた思惑
例えば、交通事故で加害者が被害者にすぐに「マイペンライ・ナ」と声をかけてくることがあります。事故を起こした後にこのような言葉をかけられれば、不快に感じるのは当然でしょう。しかし、その言葉には「こんな状況だけど、あなたは心が広いから許してくれますよね?」という暗黙の期待が含まれている場合があります。加害者側の身勝手な思いでもあるのですが、タイの人々は基本的にトラブルを穏便に済ませたいと考えています。多くの場合、相手は申し訳なさそうな表情を浮かべているはずです。その態度をよく観察した上で、穏便に進めれば問題は大きくこじれることはないでしょう。
「マイペンライ」の多層的な意味
– 調和と平和:タイ文化では、対立を避け、調和を重んじる傾向があります。「マイペンライ」は、相手に対して気を使わせないようにする表現であり、相手との関係を良好に保つための一つの手段です。
– 謙虚さ:タイ人は一般的に謙虚さを重視します。「マイペンライ」と言うことで、自分の感情や状況を軽視し、相手に対して優しさや配慮を示すことができます。
– ストレスの軽減:この言葉は、相手が何かを気にしている場合に、その心配を和らげる役割も果たします。タイ人は、ストレスやプレッシャーを避けることを好むため、「マイペンライ」と言うことで、リラックスした雰囲気を作り出します。
– 対立回避:「マイペンライ」は、問題を大きくせず、軽く流すことで、対話を円滑に進めるための表現でもあります。これにより、相手との関係を壊さずに済むことができます。
他人との距離感を重視する社会
タイ社会の寛容さは、実は「自分に害が及ばないなら干渉しない」という消極的な態度に基づいている場合が少なくありません。タイの人々はトラブルを避け、穏やかな生活を送ることを重視するため、他人の問題には適度な距離を保つ処世術を身につけています。
例えば、親族間の問題であっても、家庭内の揉め事には介入することは少なく、遠巻きに見守る姿勢が一般的です。また、この姿勢はLGBTQに対する態度にも表れています。タイ社会はLGBTQに対して表立って否定することは少ないものの、それは積極的な受容というよりも、互いの領域を侵さない距離感の表れと言えるでしょう。このように、タイの人々は本音と建前を上手に使い分けながら、笑顔で日々を過ごすことを大切にしています。
異文化理解のために
文化の違いは時に誤解や行き違いを生むこともありますが、タイに住む上で重要なのは、対立を避け、調和を重んじるというタイ文化の特徴を念頭に置いて、タイの人々の言葉や行動に隠された意味を理解することです。マイペンライというひと言に込められたこうしたいくつもの意味や背景を知っていると、より理解と敬意が深まり、円滑な人間関係を築くことができるのではないでしょうか。