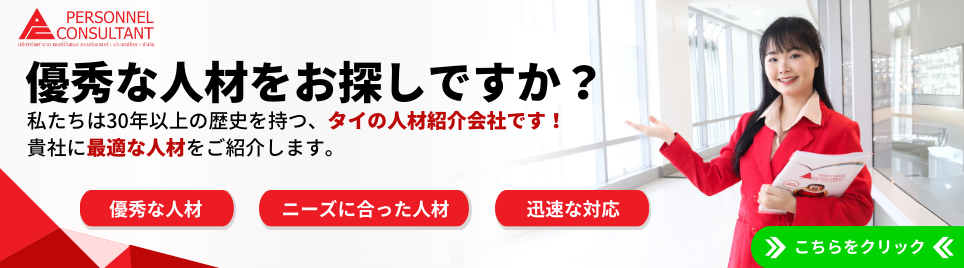タイで暮らすようになると、お米でも二期作・三期作されていたり、道端のバナナやパパイヤも次から次へと実ったりする様子に、熱帯の季候の豊かさを目の当たりにするかと思います。また、実は毎年寒季に急に気温が下がった日には低体温症からの凍死者も出ているとはいえ、凡その地域では朝晩肌寒く感じることがあるくらいで、住居にせよ衣服にせよその他装備にせよ、日本ほど準備はいらない常夏の暮らしやすさも感じるでしょう。そんなことを、身をもって経験すると、気候や風土が人の生活様式や思考に影響することについても深く感じ入るのではないでしょうか?
さて、皆さん、『アリとキリギリス』というお話はご存じでしょうか?イソップ物語の一つで、幼い頃に読んだ、あるいは、お子さんに読んで知っているという方が多いかと思いますが、読んだことがないという方のために簡単にあらすじをご紹介すると、次のとおりです。夏にアリが汗水たらして働いている横で、キリギリスは働かずに日陰で昼寝をしたり楽器を弾いて歌ったりしている。冬になって、寒さの中、食べるものもなくキリギリスはアリの家を訪れ、助けて欲しいと乞う。
ここまでは、ディテールの違いはあっても、基本的にどの話でも同じ内容です。しかし、この後の結末には、様々なパターンがあります。日本人の友人・知人に尋ねたり複数の出版社から出ている内容を見比べたりしたところ、
1.アリはキリギリスに「だから、夏の間に冬に備えておくことが大事なんだよ」と諭すところで終わる
2.アリはキリギリスに「夏は歌っていたんだから、冬は踊ればいいだろう」と言う
3.アリはキリギリスに食べ物を分けることを拒むところで終わる
4.アリはキリギリスに食べ物を分けることを拒み、キリギリスは死ぬ
5.アリはキリギリスを家に招き入れ、食べ物を分けて諭す
6.アリはキリギリスを家に招き入れ、食べ物を分けて諭し、キリギリスは恥ずかしくなる
等がありました。その中でも、3.や4.で記憶している人が多く、備えがなければ多分に死んでしまうような国では、大人が子供に「備えあれば患いなし」というメッセージを込めて勤勉の大事さを伝えるのに、敢えて厳しい現実を伝える気持ちが垣間見えます。また、自分は3.や4.で記憶しているが、子供のために買ったものを見てみたら5.や6.だったという方も結構いらっしゃったので、日本社会でも価値観や教育において力点が置かれることは変わりつつあるのかもしれません。
一方、同じ質問をタイの友人・知人にしてみたところ、3.や4.で記憶している人もいたものの、拒絶や拒絶によって死に至る結末に抵抗を覚える人が多く、中には、困っているキリギリスを門前払いしたり、無碍に扱ったりするのは酷いと言いながら、勤勉さはもちろん大事だが、タイでは仏教の教えから施すこと・弱者に手を差し伸べることも大事と語ってくれる人もいて、5.の結末での記憶の割合が多く、またこの話を知らなかったという人でもやはり5.の結末を好む人が多く見られました。
冒頭で触れたように、ベースとなる気候風土が異なるのでこのような違いが出てくることも当然ですし、この違いは優劣の判断を加えるものでもないと思います。しかし、異文化環境で仕事をする場合、このような相違があることは経営においても、特に人的マネージメントにおいても、念頭に置いて対処に活かすことが大事です。日本では因果応報的に、怠惰であることや失敗には自己責任という言葉で厳しい結末が来ることは当然とする風潮が強いように感じますが、タイの人からすると、それは周囲から慈悲心に欠けると見られることや、リーダーシップにおいても寛大さが求められていること、それ故、そのような対処が見られなかった場合には、偏狭と見られうることは意識された方がいいでしょう。