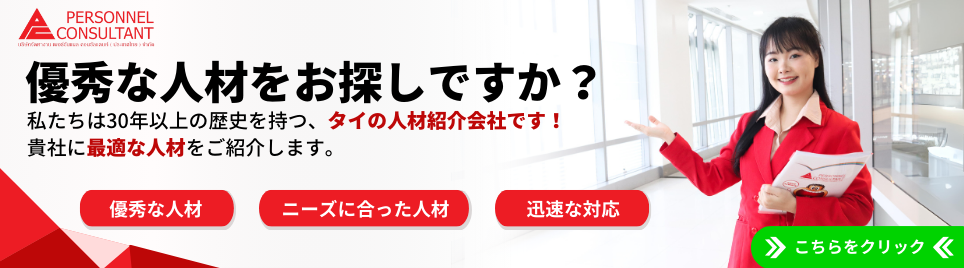<事務所選定やアテンドの参考に BTS主要駅名の意味・由来(1/2)~スクンビット(東)線編>の続きです。
今回はスクンビット(北)線、シーロム(西・南)線にご乗車いただきます!
●N1:ラーチャテーウィ(Ratchathewi)
「ラーチャ」は王・支配者、「テーウィー」は女神・文学に登場する女性で、「ラーチャテーウィ」で「王族の偉大な女性、高貴で権威ある女性の象徴」を指します。この名は、ペッブリー通の近くにあった運河にかかっていた橋の名前がラマ5世の妃にちなんでつけられたことに由来しています。
●N2:パヤタイ(Phayathai)
ラマ5世が造ったパヤタイ宮殿の名前に由来します。この宮殿はサムセーン運河の近くにあり、かつて野原だった地域の休息所として使われました。「パヤ」は高い地位を持つ者・主人、「タイ」は自由のことですので、「パヤタイ」とすることで、自由の王や独立した指導者といった意味になります。
●N3:アヌサーワリーチャイサモラプーム(Victory Monument)
「アヌサーワリー」が記念碑、「チャイ」が勝利、「サモラプーム」が戦場という意味です。1940-41年にタイが国境をめぐってフランスと戦ったタイ-仏領インドシナ紛争の際に命を失った軍人・警察・一般市民を称えるために建てられた戦勝記念塔が近くにあることから名づけられました。
●N4:サナームパオ(Sanam Pao)
「サナーム」はフィールド・場、「パオ」は的・中心点で、合わせると「射撃場」という意味です。この名前は駅のすぐ前に位置する陸軍施設に由来します。現在は、射撃や的そのものの様子は見えませんが、陸軍基地としては現役で、駅のホームからでも騎兵隊や戦車・ヘリコプターが見えることがあります。
●N5:アーリー(Ari)
「賢者の行動」という意味です。
(N6は未開通駅)
●N7:サパーンクワーイ(Saphan Khwai)
昔、パホンヨーティン通の辺りは一面の田んぼで、乾季になると地方からここに水牛が連れて来られてバンコクの農家に売られていました。そのため、地元の人々はこの地域の運河にかかっていた橋を「サパーン(橋)・クワーイ(水牛)」と呼ぶようになりました。
●N8:モーチット(Mochit)
医師のチット・ナパーサップがこの一帯に所有していた土地を国に寄付したことから、その名前と敬称で「モーチット(チット医師)」と呼ばれるようになりました。
それでは、この辺りでシーロム線に移りましょう!
●W1: サナームキラーヘンチャート(National Stadium)
日本人学校運動会で訪れた方も少なくないかと思いますが、駅のホームからも見えている国立競技場から名前がつけられました。「サナーム」は前出のとおりフィールド・場、「キラー」は運動・競技、「ヘンチャート」は国立という意味です。
●S1:ラーチャダムリ(Ratchadamri)
「ラーチャ」が王、「ダムリ」は考える・熟考する・思案するという意味です。これはラマ5世が1902年に将来のビジネス発展や人口増加を念頭に、幅広く設計・建設することを命じたラーチャダムリ通にちなんで名づけられました。
●S2:サラデーン(Sala Daeng)
この地域はもともと農地で、1893年にパークナーム鉄道が開通し、赤い屋根が特徴的な駅舎がつくられたため、「サラ(東屋)・デーン(赤い)」と呼ばれるようになったのが始まりです。
●S3:チョンノンシー(Chong Nonsi)
駅の下を流れるチョンノンシー運河に由来しています。「チョン」は溝・小道・狭い場所、「ノンシー」は黄色い小さな花が沢山咲くコウエンボク(黄炎木)のことです。
●S4:セントルイス(Saint Louis)
駅周辺のランドマークがセントルイス教会・病院であることから名前がつけられました。
●S5:スラサック(Surasak)
「スラ」が勇敢な人・勇者・戦士、「サック」が権力・能力で、合わせて、才能ある戦士といった意味になります。これは、同地域の名士チャオプラヤ・スラサックモントリーの名前から来ています。
●S6:サパーンタクシン(Saphan Taksin)
「サパーン」はサパーンクワーイ駅でも出てきました。バンコクは水の都との呼び名もあるほどで橋のつく地名も多いですね。バンコクのラタナコーシン王朝誕生200周年を記念して1982年につくられたタクシン大王橋の前にある駅なのでこの名前になりました。
今回は、延伸前のBTSの範囲で東はオンヌット、北はモーチット、西はサパーンタクシンまでご紹介いたしましたが、お楽しみいただけましたでしょうか? ご参考になりましたら幸いです。